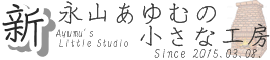――夏休みが終わり、残暑の厳しい八月二五日。
大学のような前期・後期の二期制システムの総合高校では、岩国市内のどの高校よりも一足先に新学期を迎えている。
セミの声で暑苦しいそんな中、
「ほ、本当ですか!?」
昼休みに一階の下駄箱の真上にある教室――生徒会室で、ネオがテンションの高い声をあげている。
「ええ。いつもならオーディションをして決めているんだけど、貴方たちは正式な『同好会』として活躍しているから、特別に免除しよう考えているの。ね、実行委員長?」
ネオの真正面に座っている生徒会長が、右隣にいる総合祭実行委員長――大山茜(おおやま あかね)に話を振る。
「うん。去年のあのライブからずっと思っていたんだよね。それにアタシ、夏休みにあった『アマチュア・ロック・フェスティバルin IWAKUNI』に行ってたのよ。そしたらあなた達が出てきて……ライブを見て確信したわ。麻倉さん、是非moment’sのメンバーで総合祭を盛り上げてくれないかしら?」
茜は首を少し傾けて、ふふ、と微笑みながらネオを見つめる。
その視線にネオは迷わず目を輝かせて、
「や、やりますっ! というか、ぜ、是非やらせてください!!」
張りのある声で答えた。
次の目標の焦点にして夏休みも文化祭オーディションに向けてみっちり練習していた矢先に、まさか、無条件で叶うという思いがけないレアイベントで達成されるとは! ネオは興奮収まりきれなかった。胸の鼓動が高まる。この部屋から出たら爆発しそうだ。参加してよかった!
「じゃあ、決定ね」
生徒会長が立ち上がる。
「実行委員、いや、生徒会の正式な依頼としてお願いするわね。期待しているわよ」
「はい!」
生徒会長の差し出した手をネオはがっちりと握り、固い握手を交わした。
※※※
「「「マジっスか!!!」」」
放課後、ネオの一報(いっぽう)を聞いて、メンバーの士気は一気に頂点に達した。
一〇月にある体育祭に続く学校行事――総合祭(そうごうさい)。世間では文化祭とも言う。
その企画の一つであり総合祭のメインイベントであるライブステージに、自分たちが『特別枠』として立ちあがるのだ。こんなに嬉しいことはない。
ネオたちは早速、生徒会と実行委員のご期待に添えるために選曲を決め、彼らは各パートそれぞれ自分の表現力を最大限に発揮し、他のどのステージよりも最高の舞台にするため、必死に練習を行った。
――そんな日々が毎日続き、気が付けば九月の中旬。
まだまだ残暑の厳しいこの季節。しかし、そんな暑さをものともせず、総合祭へ向けて、先に参加が決まったネオたちのテンションは、日に日に高くなっていく。
今宵(こよい)も沈む夕日をバックに、演劇部の活動を終えたプレハブ小屋で、せっせと機材を準備し、活動を始めようとした……のだが、
「ネオ先輩、遅いっスねぇー」
健斗(けんと)が呟く。
「前もそんなことがあったような」と巧(たくみ)。
腕を組んで苦虫を噛みつぶしたような顔のみちる。
三人は何の返事もないネオを待っている。
今日は総合祭でやる選曲を一通り音合わせする日。そのため、ボーカル兼リーダーである彼女がいないと練習にならないのだ。
壁に飾られている時計の針は六時半を指している。活動開始の時刻から三〇分経過。
「ほんとあの人、何やってんっスか」と不満を垂らす健斗に、
「アレでも二人の先輩でリーダーであって創部者だってのに……自覚がないのかねぇ。何度言ったら分かるんだか」
額に手を当て、呆れるみちる。
「しょーがないね。携帯に何回かけても出ないから、三人でさっさと……」
「みんな――――――っ!!」
外からネオの大声が聞こえてきた。
ややあって、
ズザアァァァ――――――ッ!!
急ブレーキで砂埃が巻き起こる。
猛ダッシュでここまで来たことをアピールして、お騒がせ娘がみちるたちの真正面に現れる。
そのまま靴を脱ぎ、
「ごめ――――――ん、遅くなっちゃった」
涼しげな顔で、ネオはすぐさまプレハブ小屋へと入っていく。
「「……」」
「あれ? みっちぃ、健斗、どうしたの?」
冷たい視線で自分を見つめる二人に、ネオは訝しそうに見つめる。巧は冷徹な二人が恐ろしいのか、背中を向ける。
みちるがネオのもとへと行く。その一歩はズシン、とプレハブ小屋全体を揺らしているかのようだ。
「?」
ネオは不思議そうにみちるを見つめる。
そして、
バッコ――――――ン!
ネオの頭にタンコブができた。
「いった――――――い! な、何すんのよ、みっちぃーっ!」
コブの部分に手をあて、左側の目を瞑(つぶ)って痛みを噛みしめる。
「なーにが、何すんのよ、だよ! 連絡も寄越(よこ)さず、三〇分も遅刻して! えぇ!?」
フン! と腕を組んで、右斜め上に顔を向けてネオを見下す。
これじゃあどっちが部長なのか分からない。
「ほんとッスよ先輩! 今日から実践(じっせん)だっていうのに、迷惑かけすぎ……」
呆れ口調で女王の発言に同意する健斗。
何よ、ナル男(お)のくせに! と文句を言いたいところだが、みちる様が壁を作っている以上、文句を言えまい。メンバーに迷惑をかけたことは事実だ。
というわけで素直に、
「申し訳ありませんでした」
空気を読んで謝罪の一言。ビシッと背筋を伸ばし、斜め四五度をキープ。
「よろしい」
みちる様の機嫌が直る。
こんなんじゃあ後輩には、『名ばかり部長』というレッテルを背中に貼られそうだ。貼ろうとしているかもだけど。
「で、こんなに遅れた理由は何? まさかあんた、素で遅刻したんじゃないだろうね? 事と次第によっちゃあ……」
「ま、待ってよ! ちゃんとした理由があるんだから! ……えーとね、描いてもらってたのよ」
「何を?」
「えっとね、確かここに……」
鞄(かばん)を開き、ネオはガサゴソと探す。
「あった!」
クリアケースから一枚の用紙を取り出し、
「じゃーん!! どーよ!!」
バーン! と自慢げに一枚の絵を三人に見せる。
ポニーテールを揺らし、穏やかな表情で笑っている女性。その表情はまるで太陽みたいだ。
でも、どことなーく誰かに……。
三人は、息ピッタリに絵とネオを見比べる。
「これ、ネオさん、ですか?」
珍しく巧が訊ねる。
その質問にネオは、周囲に花が咲き誇るようなニッコリ笑顔で、
「うん!」
と即答。
三人は、目を丸くして、
「「「ええええええっ!?」」」
と仰天(ぎょうてん)し、絵と本人を繰り返し見比べる。
「うっそ!」
とみちるが絶句し、
「マ、マジっスか……?」
と健斗が疑念(ぎねん)を抱き、
「……は、はあ」
巧は口を開けたまま。
三者三様(さんしゃさんよう)の反応に、ネオは思わずクスクスと笑い、
「にってるでしょー?」
ね! ね! ね! と賛同を求める。
しかし、
「に、似てませんよ!!」
そう言うのは健斗。
「思い違いっスよ!! だいたい、ネオ先輩がこーんな美人なわけないでしょ! 先輩はもっと、ガサツで、態度がデカくて、意地っ張りで……それが絵に表れてないっス!」
と、バカにしたように言い放つ。
それを聞いたネオはムッ! となり、
「何よ? わたしはいっつもこの絵の通りでしょ!」
「いいや、ぜんっぜん違いますって! 美人には程遠いっス!」
「わたしはいつだって美人よ!」
「いやいや、それこそナルシっスよ! カマみたいにザクッ! と殺人鬼ヘアーで斬りつけてくる時点で、美人ではなく悪魔っスよ!」
「あんたに言われる筋合いはないわよ! ていうか、わたしがいつそんなことをやったのよ!?」
「部活帰りにありました、よ!」
「それはあんたの注意不足でしょーが!」
「いーや、先輩っス! とんでもない野獣(やじゅう)っスよ!」
「わたしが野獣!? はっ、ふざけないでよ! だったらあんたは、自分のナルシストぶりをお山の上で発揮(はっき)する変態ザルよ!」
「だれがナルシスト変態ザルっスか! じゃあ先輩はジャイアニズムむき出しの、バカゴリラっスよ!」
「なにをーっ!」
んーっ! と真正面からのにらみ合い。
「もう! この二人はなんでいつもいつも……」
みちるはくしゃくしゃに髪をかきながら、しょうもない言い争いを永遠に続けそうな二人の後ろ頭に手を当て、
「いいかげんにしろっ!!」
ゴチーン!
ネオと健斗の頭がぶつかる。
「いったぁ……」
「うー……」
ネオと健斗は苦悶(くもん)の表情で赤くなった額(ひたい)に手を当てる。
「毎日、毎日ケンカばっかりして……少しは仲良くやらんか!」
「はーい」
「すんません」
「まったく」
ふあぁー、と「あたしの身にもなれ!」と言わんばかりの大きなため息が漏れる。
「それにしても」
みちるはネオを方へ顔を向け、
「ネオ、その似顔絵は誰が描いたの?」
ようやく『本題』とも言える質問をネオに訊ねる。
「誰って、みっちぃも知っているじゃない。実緒(みお)よ、竹下実緒(たけした みお)!」
「ああ、あんたがたまに昼休みに話をしている、影の薄そうな女子のこと?」
「影が薄いって……失礼ね」
友達をバカにされて、ネオはむっとした表情で前のめりになる。
「ごめん。あの子とあんなにフレンドリーになるとは思わなかったからさ」
あんな事があって、仲良くなっていることに疑っていたみちるは、改めて彼女の人付き合いの良さに感心する。
本当に人付き合いが良いのだ。普通、入学して間もない頃は同じ中学校の顔見知りがいるならともかく、どことなくぎこちなくて、「あの人は相性がよさそうだな」と探りながらクラスメイトに話しかけていくだろう。しかし、ネオは物怖(ものお)じすることなく、クラスメイトと積極的に話の輪に入り、交流を深めていった。それは当時、一緒のクラスだったみちるも例外ではなかった。
『お隣どうし、仲良くしようね!』
入学当初、中学時代の噂がきっかけで同学年から恐れられていたにも関わらず、平気な顔で話しかけてきたのだ。最初は軽々しくてうっとうしいやつだと思ったが、徐々に打ち解け、自分もギターを趣味で引いていたことを話し、ネオと共に一年間、校内や路上で必死に音楽活動して、今に至っている。彼女のおかげで、みちるにも友達がたくさんできた。
ネオとはそういう人なのだ。ワガママな部分もあるが、海よりも広い心の持ち主なのだ。その良さは羨(うらや)ましく思い、同時にそんな彼女の友達でいられることに、みちるは誇りを持っていた。本人には話せないけど。
「そういえば夏休み中、あんた、活動が終わってすぐに帰ったことがちょくちょくあったけど、彼女と遊んでいたの?」
「うん、そうよ」
「ふうん」
夏休みの活動は普段とは違い、演劇部が使わない日を利用して午前中から活動していた。そのため午後からはフリーなので、実緒の部活の休みに合わせて遊びに行っていたのだ。
「あ、みっちぃも遊びたかった?」
みちるはネオの気持ちを察して、
「いや。別にいいけど。でも、そんなに仲良くなったってことは、一緒に駅前の商店街とかで買い物したり、家で遊んだりしてたの?」
「まあね。なんてったってわたしと実緒は『親友』だからね。アレも渡したしね」
「アレって……アレのこと?」
「そっ! アレ、よ」
――それは、ネオと彼女の絆が強くなった大事な一日でもあった。
|