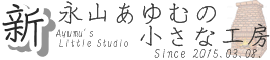「すごいね。プロのアーティストみたい。自分もあのステージ立っているみたいな感覚だったよ」
実緒の賞賛にネオは、
「そ、そう?」
少し照れた表情を見せる。
「うん、本当にすごいよ。ネオちゃんがこんなに歌が上手だなんて、びっくりしちゃった。歌詞や曲の激しさによって、こんなに表現できる人ってあまりいないよ! カラオケとかで練習しているの?」
「うん。あんまり人には言わないけど、週三回はカラオケショップで歌っているし、ボイストレ―ニングの本も買って、わたしなりに努力してるよ」
そんなネオの一面を見て、
「すごいなぁ。こんなに努力しているなんて……私なんか全然だよ」
「いやいや、実緒と比べたら全然……」
「違うよ。真っ直ぐで、必死に夢に向かって……ネオちゃんが羨ましい」
実緒は肩を落とし、
「私なんか、いつも不安に押しつぶされっぱなしだもん。部員のメンバーにもバカにされるから……だから、そんなネオちゃんが、羨ましいよ……」
泣きそうな低い声音(こわね)で、床をじっと見つめる。その姿が自分の才能に悲観しているように、ネオには見えた。
だから、
「あ、あのねえ、実緒……」
悄然(しょうぜん)としている彼女の肩を叩く。
「そんな些細(ささい)なこと、ほっときゃあいいのよ! わたしもそうしているよ」
実緒は、ネオのまっすぐな表情を見つめる。
「自分の好きなことなんでしょ? だったら前を向いて、とことんまで足掻(あが)いて、自分が納得できるところまでやらないと!」
「自分が、納得できるまで……?」
「そうよ! バカにされたっていいのよ! そういうコンテスト? に何回も堂々と参加すりゃあいいのよ! 大切なのは夢を諦めないこと! その意志があり続ける限り、奇跡は起きるわ! どんな道を辿(たど)ったとしても、最後には夢が叶う! わたしは、そう、信じる」
「ネオちゃん……でも……」
胸が苦しい表情で俯(うつむ)く実緒。
「大丈夫! わたしがついているから! ね!」
「え?」
実緒は顔を上げ、ネオがウインクしている姿を見つめる。
「道が違っても、夢に向かう情熱は……絶対に同じだわ! みんながみんな、夢が違うのは当然だよ。だけど、『叶える』というゴールへの道は、夢を持っている人すべての、共通のゴールだわ! わたしも実緒もその途中にいる。だから、一緒に行こうよ! そのゴールへ! お互い悩みとか、打ち明けながら、協力して目指していこうよ! run through(ラン スロー)だよ!」
「ネオちゃん……」
首を少し傾(かたむ)けて笑う彼女が、実緒には救いの手を差し伸べる天使のように見えた。
少し楽になった気がした。
「だ・か・ら! 見せて!」
「ええっ?」
実緒の鼻がくっつきそうなところまで迫るネオ。
「約束! したでしょ! わたしがこれを見せたんだから、あんたも早くみ・せ・て!」
「は、はいっ!」
ドアップのネオのご立腹ぶりにビビったのか、実緒は慌てて机の上にあるファイルを取る。勢いよくペラペラとめくっていく。
「あ、あった! ……はい」
ファイルからA4の画用紙を取り出し、ネオに見せる。
「ありがとう。どれどれ……おおー……!」
感嘆の声が漏らしながら、手に取った実緒のノートを見つめる。
「ど、どう……」
実緒は顔を赤くし、もじもじしながら身体を左右に揺らす。
「すごい……すごいよ! わたしたちらしいよ!」
「ホントに?」
「うん!」
ネオは頷き、お腹いっぱいの表情をみせる。
それは、夏休み前にネオが実緒に頼んだ通りの絵だった。
女二人と男二人がバンドを組んで歌と曲をかき鳴らしている姿――センターでマイクスタンド持って叫んでいる、髪のポニーテールを半袖カッターシャツと黒とギザギザな黄色い横縞模様のミニスカート。白のソックスに赤いコンバースのスニーカー。
彼女の右上にいるのは、センターにいる女子と同じ服装だが、漆黒のストレートパーマを揺らして、エレキギターを奏でている。
左上は前髪を左右に分けた半袖カッターシャツと黒のズボンを穿(は)いた、クールでイケメン顔の男子が、淡々とエレキベースを弾いている。
そして最後に、ギターとベースの二人の間に入るように、ドラムセットの前に、スティックを持ってウインクしながらキラン! と白い歯を輝かせている、ナルシストな白いバンダナの男がいる。
そう。実緒が描(か)いたのは、ネオ、みちる、健斗、巧――moment’sの面々だ。ネオ以外の三人のことは、ネオが特徴を教えてあげた。完璧に特徴をつかんだものに仕上がっている。まだ、線画ではあるが。
「これでさらにアピールできるよ! あとはこれを塗るだけだよね?」
「うん。白黒で塗ろうと思うけど、どうかな。縁取るからひとりひとりが目立つと思うんだけど……」
「実緒が思うなら、それでいいよ」
「えっ、いいの?」
「わたしは実緒の慣性(かんせい)を信じているから!」
ルンルン気分で答えるネオ。このテンションは、一日中続きそうだ。
「あ、ありがとう……はあーっ」
実緒は、ものすごく喜んでくれたことに一息つき、空気が抜けたかのようにへたりこむ。
そんな彼女を見て、
「もう、大袈裟(おおげさ)なんだから」
ネオは苦笑する。
「だ、だってぇ……」
じ、自信が、と実緒は小さく呟く。
「もう、卑屈なんだから……いい、実緒!」
ネオは立ち上がり、胸を当てながら、
「少しは自信を持ちなさい! 実緒はできる子なんだよ! 少なくともわたしはそう思っている! 卑屈になってたら、前へと進めないわよ! 恐れる必要なんてない!」
仏のように、実緒に道を指し示す。
「わたしだって、同じよ! 不安も少しはあるわ! でも、わたしには認めてくれる人がいた。才能を認められることって、本当にすごいことなんだよ! そういう友達や人が少なからずいるってことは、前に進んでる証拠! わたしはもう実緒のファンだよ! あんたを認めてるんだよ! 応援しているんだよ! 進んでいるんだよ! 頑張ろうよ!」
胸に置いた右手を力強く振り払う。
黙ったまま、実緒はネオを見つめる。本当にこの人は真っ直ぐだ、と心からそう思う。そして、勇気をくれる。
「だから、勝手かもしれないけど……わたしは、実緒のことを同じ夢を目指す『親友』で、ジャンルが違っても、『ライバル』だと思っているから。負けないわよ!」
「ええっ!」
勝手に宣戦布告するネオに、動揺する。
「なによー、嫌?」
むー、と実緒の顔を覗く。
実緒は顔を横に振ってみせる。
「う、ううん。イヤじゃないよ。ただ……」
「ただ?」
「私のことを、こんなに……」
涙が一滴、こぼれる。
大人しい性格だからなのか、今まで共に喜怒哀楽を分かち合える本当の『友達』と呼べる存在がいなかったのだろう。ネオに出会うまでは。
それが涙として、集約(しゅうやく)された。悲しいのではく、嬉しいのだ。
「ちょっ、ちょっと、実緒!」
泣いている彼女に、ネオは慌てふためく。
「わ、わたし、な、何か傷つけるようなことを言った!?」
「ううん。違うの。嬉しくて……」
大粒の涙がポタポタと白のカーゴパンツを滲ませる。
「もう、可愛い顔が台無しになっちゃうよ」
ネオは微笑みながら、ポケットにある水色のハンカチを取り出し、実緒の涙をやさしく拭いた。
――ひとり、じゃないよ。
※※※
――そしてネオは、新たにできた親友のこと――駅前にあるデパートで買い物したり、夢を語り合ったことや、お互いに悩みなどを打ち明けたりしたことを三人に話した。
「へぇー、やるじゃない」
みちるが感心する。
「やっぱり、あんたはすごいね」
「単に先輩のことをおせっかいだと思ってるかもしれないっスけどねー」
みちるの褒め言葉の裏に隠された気持ちを代弁しているかのように、健斗(けんと)が悪戯(いたずら)っぽい笑みを浮かべて茶化す。
そんな彼にネオはすかさず後頭部を、
パッコ――――――ン!
「いってぇー……」
みちるほどではないが、脳を抉られるようなゲンコツを喰らい、健斗は頭を抱える。
「まったく!」
フン! とネオは鼻息を鳴らす。
しゃがみこんだ健斗の頭を撫(な)でるみちる。
そんな二人をスルーするように、
「本当に、すごいですよ、ネオさん」
巧が話に入ってくる。
「そう?」
「は、はい。俺には、こんなこと、とても……」
自分を見つめる彼女の表情に思わずドキッとしたのか、巧(たくみ)は床を見てしまう。
「わたしにとっては、当然のことをしただけなんだけどなぁー」
「すごい」と言われたことに、ネオは微苦笑(びくしょう)して見せる。
「それができるからすごいんだよ。普通ならそういうことはなかなか言えないよ」
みちるが立ち上がる。
「それにしてもこの子、いや、竹下さんにこんな特技があるとはね。美術家とか、何かを目指しているの?」
「うん。彼女、漫画家になりたいの」
「なるほどね。道理(どうり)で美術の教科書みたいな、古臭い絵じゃないってわけね」
もう一度見せて、とネオに頼み、ネオの自画像をまじまじと見つめる。
「で、わたしの勝手でお願いしたんだけど……この同好会をアピールするためのポスターを、今、描いてくれているんだ」
「ええっ!?」
マジっスか! と痛みから復帰した健斗がサッ! と立ち上がる。
「それって、俺ら全員が入っているってことっスか?」
「当然でしょ。わたしが特徴を教えたら、それはもうそっくりに描(か)いてくれて」
「そ、そっくり……」
現実の自分をリアルに描いているのではと考え、絶句する巧。
「……タッくん、何もそこまでリアルじゃないわよ。ファイナルファンタジーじゃあるまいし。ていうか第一、ゲームみたいにCGで描かないわよ」
巧の考えていることを見透かすようなツッコミを入れる。
「ちゃんと漫画にでてくるようなキャラになっているよ。あとはカラーを塗るだけだから、期待しててね」
ふふっ! と笑みをこぼしながら、ネオはウィンクして見せる。
「おお、それは楽しみだね」
「オレのカッコよさを際立たせてくださいよ」
「……ま、待っています……」
みちる、健斗、巧の順にそれぞれ期待を寄せた。
そのことを実緒に伝えなくっちゃ! とネオは内心思ったが、
「うん……でも、ちょっと……」
いきなり、気難しい顔に方向転換する彼女に、三人は、ん? と目を丸くしながら見つめる。
「まさか、これだけ期待しといて、『実はウソでしたー』とか言うんじゃないだろうね。エイプリルフールはとっくに過ぎているんだけど」
みちるが目を細める。
ネオは慌てて両手を開いて左右に振り、
「ちがう、ちがう! ただ、気になることがあって……」
「気になること……?」
うん、とネオは頷き、普段見せない真剣な表情を見せる。
「最近気づいた違和感なんだけど、最近、表情が暗くなっているような気がして……」
「暗い?」
首を傾げるみちる。
「夏休みは、ものすっごい明るかったの。テンションも高かったよ。ところが、学校が始まってからの昼休み中の実緒は、明るいんだけど、どことなく暗くて……それが、だんだん目に見えてきて……う〜ん、わたしの思い違いなのかなぁ……」
ネオは腕組みをして天井を見つめる。
「まあ、確かに元気なくもないような気もないけど……」
みちるも顎に手を当てて考え込む。
そう見えるんだよ、とネオははっきりと言える。
休み時間や昼休みに会話するときも、日に日に気が沈んでいるような……空元気で無理に笑っている表情を作っているようには見えたし、授業中もしゅんとしていて、度々、先生の質問に答えられなかったり……彼女らしくもないのだ。
そして今日も、だ。
下駄箱で別れるとき、
『また明日ね! 実緒!』
『う、うん。また、ね』
表では明るく見えたが、歯切れの悪さに裏側にある重く、暗い表情がネオには見えた。まるで、「別れたくない」と心の中で訴えていたような……部活で何かあったのだろうか。
「うー、気になるなあー」
頭を抱えて項垂(うなだ)れるネオ。
仕方がないのだ。友達のことになると、どうしても本気で気になる。
「こういうときって、わたしから聞くべきなのかなぁ……?」
「大丈夫よ」
みちるがネオの前へと出る。
「そんなに仲良くやっているのなら、楽しいと思っているわよ。寂しいんじゃないの?」
「だといいんだけど……」
「まあ、人間、誰にだって言えない悩みの一つや二つはあるからね」
「うーん、でもなあ……」
精一杯の作り笑顔っぽかった実緒の表情が、ネオの脳裏に焼き付く。
とにかく、煮え切らない気持ちでいっぱいなのだ。
「誰にだって、言えない事はある」というみちるの言葉も理解できる。でも、吐き出すことでスッキリすることだってあるはずなのだ。そのための友達なんじゃないのか、とも思う。
――本当に黙って見守るべきなのか。
「ネオ、心配し過ぎだよ」
ネオは右肩を優しく叩くみちるを見つめる。
「そんな風に考えることは良い事だけど、言いたくない事まで踏み込んで『話してよ!』と押し付けたら嫌われてしまうよ」
『嫌われる』という言葉に、ネオはビクッ! と背筋に電撃が走った。
「そ、そう?」
「そう! 世の中近づ離れずの距離で語り合うのが一番! ずんずん前に出たら、逆に言えなくなるし、無神経って思われてしまう。友達付き合いも駆け引きが重要だよ。大丈夫さ。時が来れば、そのうちあっちから悩みをぶつけてくるよ、きっと」
「そう言われると、確かに……」
みちるの言い回しに、自然と納得してしまう。
「よし! 分かったんなら堅苦(かたぐる)しい話はもうおしまい! あーあ、活動開始から五〇分も経過して、日も落ちちゃったよ。誰かさんのせいで」
みちるは踵(きびす)を返して、定位置にあるエレキギターのケースを開く。
彼女に嫌味っぽく言われて、
「うっ……悪かったよ……」
そこには責任を感じたのか、ネオは素直に謝る。
「健斗も巧もすぐに準備をする!」
二人もみちるの指示に「うっス!」、「はい」と、自分の定位置で準備を始める。
「今日は総合祭で歌う楽曲の音合わせをするんだから、本番だと思ってやるように! 特にネオ!」
ビシッと、黒いエレキギターをストラップで吊るして左肩にのせた状態で、右手の人差し指で、ネオの顔を差す。
「え? わたし!?」
思わず右手の人差し指を自分に差す。
いやいやわたし、準備OKなんですけど。
「そう! 竹下さんの事を考えるのはいいけど、リーダーらしくきっちりやってよ! あんたが元気じゃないと、ウチらはなーんにもできないんだから!」
ああ、そういうことか。
みちるなりの気遣いに内心感謝しながら、
「わかっているわよ!」
と強気で、威張(いば)った態度を取る。
――うん。みっちぃの言う通り、信じよう。わたしと実緒は『夢』を追いかける親友だもの! 大丈夫!
親友になる以前から、実緒のことは信じているのだ。ここで信じないでどうする。わたしらしくもない。
ネオは開き直り、準備ができた三人に向けて、いつものハイテンションな声で、
「よぉーし! 今日も爆音で夜を明るく照らすわよ!!」
「「「おおーっ!!」」」
部員達はネオの大声で盛り上がる。
そして、練習という名の夜の宴が今日も始まった。
――総合祭まで、あと二週間と三日。
※※※
「ふう……」
落ち込んでいるような表情で、専門教室棟の階段を歩く実緒。
やはり、相談した方がよかったのだろうか。いつも応援してくれる彼女なら、力を貸してくれただろうか。
いや、これは自分の問題だ。人に助けられても、結局は自分が解決しなければ意味がないのだ。せっかく、彼女は目標とした夢舞台へと立てるのだ。こんな大事なときに、巻き込むわけにはいかない。
気がつけば、美術室の前にいた。
「お疲れ様です」
実緒は中へと入る。
部員達は実緒を一瞥すると、声もかけずにすぐに顔をそらし、それぞれ作品の制作に向けて準備をしていた。まるで、「竹下さんの居場所はここにはない」と背中で言っているように見える。
部員達の素振りに、実緒は苦しそうな表情で窓際においてある白い布がかけられているキャンバス――自分の座席へと向かう。
席に座り、布をとる。
すると、
「!」
――実緒の頭の中が真っ白になった。
第二章END
|