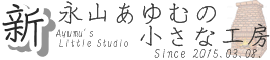実緒の家の近くにある、つい最近できたような真新しい公園の小屋で、ネオとみちるは雨宿りをした。ベンチは冷たく、全身の体温を下げていく。
雨は相変わらず強く降り続き、大きな水たまりもできている。わたしが流した涙の量を表しているみたいだ、とネオは思った。
ネオはその場で座ったまま、潤んだ瞳で公園の風景をじっと見つめた。目の前に置いてある二つの――ネオとみちるの自転車が冷たく光る。
どうして、気がつかなかったのだろう。その言葉ばかりネオの頭に浮かぶ。実緒の心の叫びに応えられなかった悔しさで、胸が痛んでいる。自慢のポニーテールも、髪も花が元気を無くしたように、へたれているように見える。
「ネオ」
公園内にある自販機に立ち寄っていたみちるが帰ってきた。
「はい、缶コーヒー。冷める前に飲みな」
「うん……ありがとう、みっちぃ」
みちるはネオの隣に静かに腰を下ろし、コーヒーを飲む。ネオもそれに見習う。冷え切った身体が温まっていく。しかし、ネオの心まで熱が通ることはなかった。ため息が漏れ、二人の間に沈黙が続く。
ややあって、
「……美術部の部長から聞いたよ」
みちるが破いた。はぁー、とため息をついて、
「同じクラスにそんなヤツがいるとは思わなかったよ。あいつ、大口は叩くけど、普段はクラスメイトとはうまくやってるってのに、まさか裏でバカなことをやっていたなんてね。……ホント、高校生になっても『正しい』と『悪い』の区別もつかない自己中ががいたとはね。ホンッと、学校じゃなかったら、空手でボッコボコにシメてやりたかったよ」
みちるもネオと同じ気持ちだった。悔しさと憎悪(ぞうお)で飲み干した缶コーヒーを手の握力でぎゅっ、とへこませる。
彼女も同じ気持ちをもっていることに、ネオは少し安心した。
「実緒は、向井のせいで深い傷を負ってしまった。わたしの手をつかめないほどズタズタにされて……」
くやしいよ、とネオは項垂(うなだ)れてしまう。
「あんな奴のせいで……親友としての時間を、簡単に無かったことにされるなんて……!」
「ネオ……」
再びネオの瞳から涙が頬(ほお)を伝っていく。滲み出る彼女の悔しさに、みちるもどうしようもない気持ちでいっぱいになる。
「ほんと、どうしたら、いいのかな。もう、終わりにするしかないのかな……」
「え?」
終わり、というネオらしくもない発言に、みちるは思わず落ち込んでいる彼女の方へと振り向く。
「いつだってわたしが精一杯やれることはやってきたけど……実緒は、わたしたちのことまで『怖い』と思っているんだよ。そんな彼女と、どう向き合えばいいの? どんなことがあっても、絶対に離れたりしない、ずっと友達だって伝えたいのに……分からないよ……」
両手で顔をふさぐネオ。
一人でずっと考えるネオ。
たった一人で苦しむネオ。
相談はするけど、頼ることを知らないネオ。
――そんなネオに、みちるはふつふつと、苛立(いらだ)ちが募る。
どうして。
なんでなんだよ……。
いつだってそうだよ!
なんで、なんで、ボロボロになっても、「力を貸して」って言ってくれないんだよ!
あたしはそんなに頼りないのかよ!?
――なんで頼らないだよ!
「やっぱり、もう諦めて……」
その言葉をネオが発した瞬間、
「バカ!!」
みちるは立ち上がり、放心(ほうしん)状態のうじうじネオを鋭い目で見下す。
「み、みっちぃ……」
「なんで、なんで、いつもいつも一人で考え込んで、無茶な事ばっかりして、ひとりで傷つこうすんだよ!」
「だ、だって、これは、わたしのもん……」
「カッコつけんじゃねぇ!」
みちるの叫びがネオの言葉を振り払う。
「それこそいい迷惑だよ! 少しはあたしを……あたしたちを頼れよ! みんなで力を合わせて、手をつないで、そして前進するのがアンタの創ったバンド――moment’sだろ!」
「……」
みちるの涙で潤んだ瞳に、ネオの心が留まる。
普段見せない顔だ。
「あたしにも、あたしにだって、竹下さんが不登校になった非はあるよ! あんたが竹下さんの本気で大事にしていたのに、あんなことを言ったんだから。その方が、お互い傷つかなくて済むと思ったから……」
「ううん、違うよ! みっちぃの言ってることだって正しいよ!」
「違わない! あたしがあんなことを言ったからあんたたちが……!」
「違う! 常に一緒にいて、気づかなかったわたしがいけないの!!」
「いいや! あたしが悪いんだ!!」
「いや、わたしだよ!」
「違う! あたし!」
「わたしだってば!」
自分の主張が通じないみちるに、ネオもとうとう立ち上がる。
お互い、自分の気持ちを譲らず、ぶつかり合う。
「あたし!」
「わたし!」
「あたし!」
ボクシングのようにラリーの応酬(おうしゅう)が続く。
一分、二分と。
そしてラウンド終了。
――はぁ、はぁ……。
決着がつかず、唇が渇(かわ)き、息が漏れる。
みちるは右手で唇を拭いて、
「やっとネオらしくなってきたじゃないの」
うっすらと笑みを浮かべる。
生意気なネオが戻ってきて、少し安心したのだ。
「みっちぃ……」
「まぁ、何はともあれ、あたしもネオの気持ちと同じだよ。それにこの問題は、moment’sの問題でもあるんだ。だってそうでしょ。あたしたちのためにポスターを描いてくれてんだろ。だったら、竹下さん、いや、実緒も立派なあたしたちメンバーの内のひとり、だろ? それにあたしだって、あんたのおかげでここにいるのよ。あたしを無理矢理立ち直られた恩人に、何も返さずにどーすんのって話よ」
みちるは左目だけ閉じ、ウインクをする。
「だから……」
そしてネオの両手を握り、
「助けよう、実緒を!」
みちるは真剣な表情で見つめるネオを見つめた。しかし、
「で、でも、助けようって言っても、どうするの……?」
救いの手が欲しいと思わせるような相貌(そうぼう)で、ネオは彼女を見つめ返す。
「確かに……奇麗事(きれいごと)ばかり言っても彼女に届くことはまずないだろうね。だけど、あたしたちには、あたしたちにしかない唯一の、とっておきの武器があるじゃない!」
「えっ?」
「あたしたちは何の活動をしているの?」
「バ、バンド」
「そう。だから?」
「う、歌!?」
「正解!」
みちるは大きく頷く。
「そう。ネオが大好きな、歌。これしかないよ。あたしたちは、『前進』というコンセプトのもと、みんなの背中を音で後押しして、みんなで前に進むんだろ? だったら、こっち側に引っ張り出すことだってできるだろ?」
「!」
そうだ。そうだよ……。
ネオは思わず口に手を当てる。
「ネオ、あたしはね、あんたの、諦めずにみんなで前を――明るい未来に向かって行こうと言う姿勢が好きだから、ここにいる。中学で恐れられていたこんなあたしを、ネオは無理矢理引っ張ってくれた。だから、不器用でもいいんだよ。今日、明日で届かなくてもいい。大事なのは、それを何度も貫く姿勢だよ! 歌でメッセージを伝えようよ。あたしたちのできることで、実緒に届けようよ!」
……。
――みっちぃの、言う通りだ。
歌。それは、自分の気持ちを必要以上に伝えられる、唯一の魔法。輝くことを許してくれる、今一番誇れるもの。
――なんで、すぐ近くにあるものを忘れていたのよ! 今こそ、わたしの想いを『歌』に込めないと! 『歌』の力を信じないと!
友人のおかげで、道が開けた気がした。
ネオから暗い表情が消え、決意を固めた真剣な表情へと変わる。
「ありがとう、みっちぃ。わたし、実緒のために、歌うよ! どんな結果になっても、やってやるわ!」
そんなネオを見て、みちるは彼女の両肩を再びがっちりとつかみ、
「よーし、それでこそネオよ!! いや、ネオだけじゃない! あたし、健斗、巧――moment’sのマジのマジのマジをぶつけて、あの子の笑顔と取り戻して、みんなであのゴミクズの鼻の下をボッキボキに……!」
「み、みっちぃー、気合い入れ過ぎぃーっ!」
ヒートアップしすぎて、みちるは無意識にネオの肩を揺らしていたことに気づく。
「あ、ごめん。つい……」
ピタッ、と動きが止まり、手が離れる。目が回ったように、前後ろへ揺れた感覚が残る。
「もうー、暴走しないでよね」
ぷくーっ、とネオは顔を膨らませる。
その顔を見て、もう大丈夫だな、とみちるは思った。いつものネオだ。
それがなんだか妙におかしくて、ぷっ! と吹いて、ハハハハハ! と思わず笑った。それにネオもつられ、お互いに笑い合った。心が、少し軽くなった気がした。
すると、
「あ、雨が……」
ネオは空を見上げた。雨はいつの間にか止んでおり、雲間から差し込む光が二人を照らしていた。
「きれいだね」
「ああ」
みちるもネオの隣で見つめる。
まるで希望の光だ。これはきっと、前に進めという暗示だ。この光を、実緒にも見せてやりたいとネオは思った。
「さぁーてと!」
みちるが背伸びをする。
「そうと決まったら、今日の練習から何とかしないとね。まあ、まずはあの二人を説得するのは……なんとかなるけど、問題は曲だな。こればっかりは話し合わないとね。よし! じゃあ、学校に戻るよ、ネオ!」
「うん」
みちるは置いてある傘を自転車のかごの中に入れ、自転車を押し出し、先に小屋からでていく。
先を行く彼女にネオは、何か言わなくちゃ、何か言わないと……、そんな気持ちが強くなる。
そして、
「み、みっちい!」
「何?」
「あ、あのね……。来てくれて、ありがとう! そして、ごめん。わたし、これからも素直に言えないかもしれないけど……わたしの友達でいてくれる? みっちぃを頼っても……いい!?」
友人に対して言いたかったことを全て吐き出し、ネオは長い息を吐いた。
ややあって、みちるは自転車に乗り、右手を挙げ、
「当たり前だよ」
と言い、公園を出ていった。
その様子に、ネオはほっとした。
そして、その背中に向かって、「ありがとう」と心の中で伝えた。
「……って、ま、待ってよー!」
自転車の鍵を開け、ネオはすぐにみちるの下へと向かった。
※※※
「――先輩のお願いなら、しょーがないっスね!」
プレハブ小屋で、昼にあった出来事をネオから聞いた後輩の野上健斗は、開き直った態度で受け入れる。
健斗の隣にいる同じ後輩の伊藤巧も、
「……やりましょう」
とクールな態度を装(よそお)いながらうなずいた。普段は表情を変えず、何を考えているか分からない巧だが、このときだけは彼の真っ直ぐな瞳の中に、熱いものがこみあがっていることを、ネオは理解できた。
みちるは、ネオの左肩に手を置き、「言ったとおりだろ?」と言っているみたいに、無言で彼女にウインクしてみせた。
本当に、いいメンバーが加わってくれたものだ。
「二人とも、ありがとう!」
ネオは、健斗と巧に最大限の感謝を礼で表す。
かしこまる彼女に一瞬戸惑(とまど)うも、ニッ! と健斗は口を横に広げて、
「オレらに礼は不要っスよ、先輩。どーせ、嫌だとか言っても、みっちぃ先輩が説得するんでしょ? 何が何でもやるって顔をしていましたよ。だったら、先輩の言うことを、オレたち一年が文句を言う義理は無いっスよ。それに、そんな話を聞いたら俺も黙っていられないッス!タクもそうだろ?」
健斗は隣にいる巧に、なあ? と同意を求める。
「……う、うん。俺たちの曲で、実緒先輩が前へ向いてくれるのであれば、これほど嬉しいことはないですよ……それこそ、moment’sじゃないですか!」
巧らしからぬ熱い言葉に、ネオは一瞬、口を丸く開け、
「も、もう、タっくんのくせに、格好いい事を言っちゃって!」
このこの! とネオは彼の背中を叩く。巧の顔がすぐに赤くなる。
「まっ、偉そうに言いましたけど、結局は、ネオ先輩のワガママにオレたちはいっつもついて行っているだけっスからねー」
へへん、と健斗がネオに向かって悪戯(いたずら)っぽい笑みを浮かべる。
ネオは『ワガママ』というワードに引っ掛かり、
「わ、ワガママって何よ!?」
不満げな表情で健斗を見返す。
「そのままを言っただけですよ! いっつもオレたちに何も言わずに、選曲も決めたり、選曲が合わないものだって、『部長の権限(けんげん)』で意地でも押し通そうとするし……ワガママ以外の何物でもないじゃないっスか!」
「なにをーっ!」
両者の間に見えない火花が散る。
しかし、
「こら! 喧嘩をしている場合じゃないだろ!」
とみちるに押されて、お互いの額をゴツン! とぶつけられる。
「いったぁーい!」とネオ。
「……ってー」と健斗。
はぁー、とみちるからため息が漏れる。まったく、何度漏れたらいいのやら。
「と・に・か・く! 時間がないんだ! 彼女に届く曲は何か、とっとと考えるよ!!」
命令するかのように、みちるは三人に指を差す。
「うーん、そうは言っても……オレたちの気持ちを伝えられるドストレートな曲っスかあ……」
腕組みしながら考え込む健斗。
「そうですね……」
巧は目を瞑(つぶ)って顎(あご)に手を当て、うーん、と呻く。
「……ウチらで作ったので当てはまるとしたら、『wind』とか『run through!』 とかだと思うけど 、疾走(しっそう)感のある曲ばっかりだからねぇ」
天井を見上げるみちる。
「ですよね。バラード系は全然作ってないっスから……」
「やっぱり、コピーするしかないのかな」
とネオ。
うーん……。
考え込み、しばらく沈黙が続く。
「ねぇ」
ややあって、ネオが三人に声をかける。
「みんなに提案があるの」
「どうしたのよ。改まって」
と、みちる。
「ちょっと、無理なお願いなんだけど」
「無理なお願い?」
不思議そうに見つめるみちるたち。
「うん。一週間でやるのは厳しいかもしれない、いや、そうなんだけど……新曲を作ってみようよ。いつも通り、私が作詞で、みっちぃが作曲、そして健斗とタッくんが編曲で!」
「ま、マジ?」
ネオの提案に、みちるをはじめ、健斗と巧も驚いた形相(ぎょうそう)を見せる。
ネオは、そう、と言い、
「この問題はきっと、自分の言葉じゃないとダメだと思うの。確かに説得力のある有名アーティストの楽曲のコピーはいいかもしれない。でもそれは、人の力を借りたという事実があるから、言い方が悪いけど、わたしたちの気持ちなんてこれっぽっちもこもってない。なら、自分たちの気持ちを前面に引き出した、この世にたった一つしかない、『わたしたちだけの曲』を作った方がリアルに、実緒に届くんじゃないかなーと……」
やっぱり、うまく言えないや。
こんなの無謀(むぼう)だよね。今までだって、制作に二、三週間かかっているんだから。やっぱりやめよう、とネオが言いそうになったその時、
「ネオ」
みちるがネオの前へと歩み寄る。
彼女の両肩に手をあて、
「いいよ」
彼女の答えにネオは思わず、
「いいの?」
と訊(き)きかえす。
みちるは無言のまま、うん、と頷く。「それが竹下さんに伝える一番の方法だよ」と言っているみたいだった。
そして後ろを振り向き、
「健斗、巧もそれでいいね?」
みちるへの返答に、「うっス!」と健斗、「はい」と巧。
「よし、決定!」
みちるはもう一度、ネオの顔を見つめ、
「作ろう、あの子に届ける歌を!」
みちるの表情は、真剣そのものだった。
「……うん!」
力強く頷くネオ。
みちるは手を軽く叩き、
「それじゃあ早速始めるから、各自準備して!」
「うっス」
「……はい」
みちる、健斗、巧はそれぞれ楽器を取り出し、準備に取り掛かった。
ネオはそんな心強い彼らの背中を見て、
――ありがとう。
心の底から思った。
わたしには仲間がいるんだ。ひとりで必死に考える必要なんてないんだ。分からないなら、力を貸してもらえばいい。そうやって、力を合わせれば扉は必ず開いてくれる。それをもっと早く気づいていたら、とも思った。
でも、これでいい。
実緒にも、この絆という力で、『実緒の背中にはわたしたちがいる』ことを教えることが出来るのだから。
――よし。
ネオはこの想いを、今までの音楽活動の中で、最高の歌詞を書いてみせると誓った。
これからの、『わたしたち』のためにも。
※※※
「うーん」
時計の針は二十三時三〇分を指そうとしていた。明かりが消えた暗い部屋で、ピンクのパジャマを着たネオが、布団の中で呻っている。普段のポニーテールとは違い、長い髪を降ろしている。
彼女の家は、築三十年の古ぼけた二階建ての木の家で、実緒の家がある場所よりも緩やかな坂の上にできた団地にある。
ネオは二階の右の部屋を使っている。ちなみに左の部屋は、兄――広樹(こうき)が使っている。
机の上は学校で使っているノートや音楽雑誌がぐちゃぐちゃに散乱しており(その上、服も置きっぱなし)、女性らしからぬ汚部屋っぷりだ。よく堂々と友達を入れることができるものだ。
その空間でネオは、後ろに置いてあるMDコンボから聴こえる一〇代に絶大な人気のあるラジオ番組『SCHOOL OF LOCK!』を聴きながら、用紙とにらめっこしていた。
「ううーん」
メンバーにああは言ってみたものの、なかなか歌詞が浮かんでこない。
綺麗な言葉の方がいいのかなと考えるが、出てくる言葉はストレートな言葉ばかり。器用な言い回しの歌詞を書くのは、ネオにとっては難しかった。
MC(教頭)の名台詞である『高二はいいぞ!』を聴いたところで、机においてあるMDコンボのリモコンを取り、電源を切る。
「ふう、焦っていても仕方ないか」
とりあえず、夜の空を眺めてみるか。もしかしたらピンとくるかもしれない。
ネオは立ち上がりベランダに出て、夜風に当たった。
「うう……寒いなあ」
真昼の暑さはどこへいったのやら。全身がぶるっと震える。
今日は満月のようだ。雨が昼に降ったせいか、雲一つなく、星と共にネオを明るく照らしている。それはどことなく、自分の身の心配をしているようにネオは思えた。「大丈夫?」と優しく語りかけるみたいに。
すると、
「ん?」
右ポケットに入れていた携帯が震動する。
「こんな真夜中にいったい……」
怪訝な表情でネオは携帯を取り、確認する。携帯には『アホ優太』と表示されている。
「優太……」
ネオはすぐに通話ボタンを押す。
『よ、よお、ネッチー』
携帯からいつもの幼なじみの声が聴こえてくる。
「だからネッチーじゃない! まったく、アホ優太のくせにこんな時間に何よ」
『あ、アホ優太っておまえ……』
「アホなんだからしょーがないじゃん!」
『うっせぇよ。せっかく人が心配して電話したっていうのに』
「あ……見てたの……?」
『ああ。下駄箱から勢いよく外へ出ていくもんだから、びっくりしたぜ。事情は長里さんから聞いたけど、大丈夫なのか?』
優太の疑問にネオは、へん!、と切り捨て、わざといやみっぽく、
「あんたのように脆くはないですからねー。わたしには簡単には砕けない鋼鉄の心があるからねー」
『過去の話を蒸し返すなよ。俺だって変わったんだから。おまえと、アイツのおかげで再びソフトテニスができるようになったんだから』
「過去といってもまだ半年前の話じゃないのよ」
いたずらっぽく言うネオ。
優太は半年前の三月(二年生進級前)――、中学時代の部活での責任感に苛まれて、立ち直れなかった。そんな彼を、ネオとみちるを始め、八月の夏の大会後に引っ越しして、別の高校へと行った相方のおかげで、再びソフトテニスのコートに立つことができたのだ。
『だから蒸し返すなって。ったく、心配した自分がバカみたいに思えるじゃねーか。とにかく、元気そうでよかったよ。今、書いていたのか?』
「うん。だけど、なかなか歌詞が浮かばないから月を見てる」
『そうなんだ。俺も外で眺めてる』
「あれ? 優太ってロマンチストだったけ?」
『そんなんじゃねーよ。おまえと電話するのを家族に聞かれたくないだけだ』
「あっそ」
あっそ、とそっけない幼馴染みへの返答に、素直じゃないなーとネオは思う。不思議だ。素直になりたいけどなれない、それが『幼馴染み』という関係なのだろうか。
『しっかし、月ってすげーよな』
「何が?」
『だってさ、月を眺めてたら悩みだとか、悲しい気持ちとか、吹き飛んじまうもんな』
「え? 吹き飛ぶ?」
電話越しにきょとんとするネオ。
『そうだよ。神様のように俺らを見守ってるつーか、なんか試合前とかに眺めたらホッとするんだよな。色んな人が俺のように悩んでいるって。同じだって言ってる気がして……』
「同じ……」
優太の一言に引っかかるネオ。
『ん?、どうしたネッチー』
幼馴染みをよそに、一段と輝く満月を眺めるネオ。
――月……見守る……神様……。
……これだわ!!
ごちゃごちゃになっていた頭の中が、急にスッキリした。
今書いている歌詞と眺めている満月がつながった。
「月って、みんなのことを見守っているように見えるよね。だったら、月から実緒が元気でいるようにと見守っている……。そういう歌詞にすれば……!」
いける!
優太はやっぱりロマンチストだ。
「アホ優太のくせに、いいこと言うじゃない!」
『へ?』
「サンキュー」
『え、お、おい!ネ……』
――これよ、これ!
ネオは、すぐに部屋に戻って再び布団に寝そべり、置いてある紙に鉛筆で歌詞を書いていった。優太の助言で、すらすらと言葉が浮かぶ。
――実緒! アンタは、ひとりじゃない!
彼女への想いを歌詞に込めていくネオを、月が優しく見守った。
|